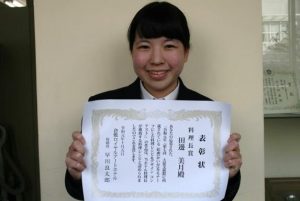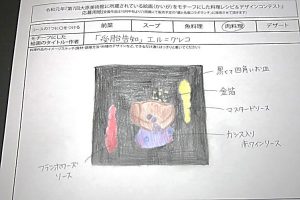令和元年12月18日(水)健康スポーツコース1・2年生は倉敷芸術科学大学に訪問し、春と冬の恒例〝体力測定〟に挑みました。
【内容】
①Inbody(インボディ)による体脂肪や筋肉量やヘモグロビンの測定。
②坂道ダッシュ・・・坂を全力でダッシュ。
③メディシン投げ・・・重りの入ったボールを前から後ろへ、後ろから前へ投げる。
④T字ダッシュ・・・T字に置いてあるコーンにタッチして走る、
⑤ジャンプ・・・ジャンプした際の滞空時間を測る。
⑥ベンチプレス・・・重りを持ち上げる。
《生徒感想より》
〇定期的に測定することができて、これまでの自分のトレーニングを見直すきっかけにもなるし、これからどこの部 分を鍛えていかなければならないかが分かる。健スポでよかったなと思います。
〇陸上部としてダッシュが速くなっていることや跳躍して滞空時間が伸びていたので、練習の成果が出せ安心しました。
〇今回のベンチプレスは70㎏以上まで上げられたのでよかったです。次のベンチプレスは90㎏を目標に、筋トレをどんどんしていこうと思います。